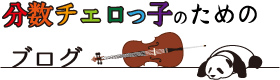発達障害と音楽教育。
- 2020.07.15
- 母さんのひとりビブリオ
- 発達障害, 音楽教育, 中嶋恵美子さん
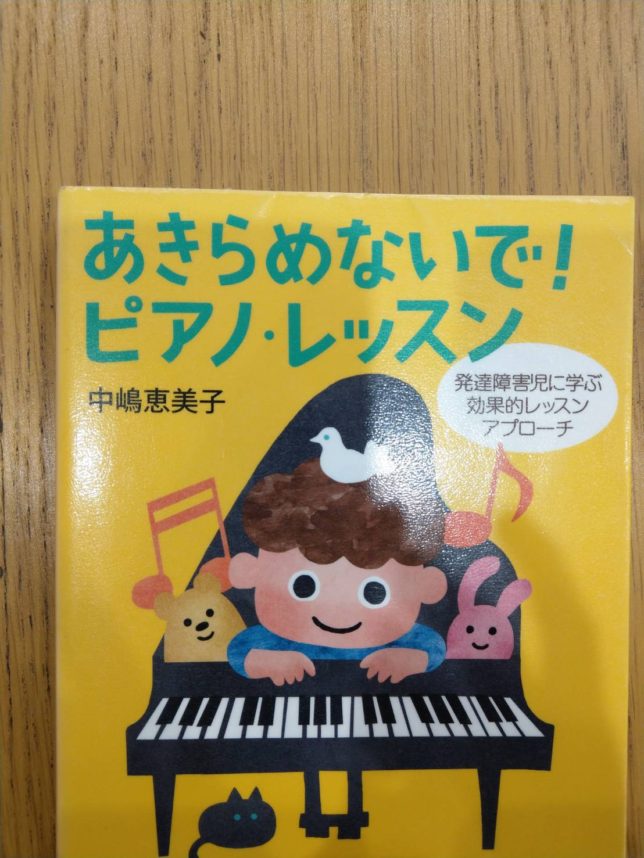
中嶋 恵美子著『あきらめないで! ピアノ・レッスン ~発達障害児に学ぶ効果的レッスンアプローチ~』
ちょうど最近、発達障害に関しての本を読んだばかりだったので、ついつい読みたくなりました。
著者の中嶋 恵美子さんは国立音楽大学音楽教育学部幼児教育専攻卒のピアノの先生。
ある日、
「うちの子、発達障害児なのですがレッスンしていただけないでしょうか?」
という電話がかかってきました。
当時の中嶋先生は発達障害に関する知識はまったくなかったのですが、
「せっかくの出会いだから大切にしたい。障害を理由に断るのは嫌。」と受け入れたそうです。
そこから様々な子たちを前に中嶋先生の工夫が始まります。
この本に書かれている子の一例として、
・最初から完璧に弾けないとイライラする子
・間違えるのを極度に恐れる子
・間違いを指摘されるとイライラする子
・間違えるとイライラする子
・時間に固執する子
・曲に執着する子
・新しいポジションを受け入れられない子
・イスにじっと座っていられない子
などなど…。
あれ?
子供って何かしらどれかに当てはまりませんか?
わが子も、
譜面の読み間違え、見落とし、先生に言われたことをすぐに忘れる、曲を間違えたら最初から弾きたがる、終わった曲なのにとにかく弾きたい!松ヤニ・メトロノームをしょっちゅうなくす、足をブラブラする、過去にはレッスン前にお教室の空気清浄機が気になりずっとその風が出てくるところを見ている…などなど上げたらキリがありません。
小さい頃に音楽教室の体験入学では、踊りや歌には一切加わらず、DVDの機械のスイッチをずっと押してました…。
発達障害って言葉はどうしても大げさに聞こえます。
が、知り合いのドクターに言わせると、
「子供はみんな発達障害みたいなもの。だって脳がまだ成長途中だからね。」
とのこと。本当にその通り。
なのでこの本は発達障害関係なく、子供の音楽教育にとって非常に参考になりました。
大人って思った以上にアバウトな指示しかしていなくて、子供にしてみれば「それってどういう意味?わからない。」ってことが多い。
「汚い音って?」「フォルテって?」
だからこの本では「わからない、できないではなく、大人が工夫して子供にとって具体的にわかりやすく伝えましょう」って事が書かれています。音の大きさを数値化したり、音の長さをペンで書いて可視化したり。
楽器や発達に関係なく、子供の音楽教育について「なるほど!」と思うことばかり。
以下、目次です↓
■序章:教室に発達障害の子がやってきた
■第1章:その子の個性を知ろう(幼児の世界 / 自閉症スペクトラムの子 / 知的障害の子)
■第2章:その子の理解力を知ろう(言葉が通じますか? / 文字が読めますか? / 2つの黒鍵と3つの黒鍵の区別がつきますか? / リズム譜が読めますか? / 指番号を覚えられますか? / 線上と線間の区別がつきますか? / 音の長さを理解できますか?)
■第3章:その子の身体能力を知ろう(幼児の身体発達の順番 / それぞれの身体能力に応じたアプローチ方法)
■ピアノ教室Q&A
などなど。
その中でも
「理解できているが、テンポが安定しない子」
について書かれていた本文で、
「自閉症の生徒さんは音楽を先に先にと進めたがる傾向があります」
とありました。
いや…自閉症に限らず、子供はほぼほぼ先に進めたがります。わが子もそう。
最後にどんどん早くなる曲なのに、最初っからとばしすぎて終盤ワケのわからんことになってました。いつも見切り発車です。いつも伴奏の先生が上手く導いてくださっていますが、それでも見切り発車しがちです。
たまに動画の撮影で小さなお子さんがたくさんいるお教室の撮影もしたりしますが、みんな曲の終わりにかけてだんだん速くなっていって、先生方が設定した終了時間より、いつもかなり早く終わります。そういうもんです。
そもそも、楽器を弾くこと自体がものすごくマルチタスク。大人がやるのでも大変なのに、それを子供がやっているんです。
チェロの場合なら、右手で音を出して、左手で音階をつくって、目で楽譜を追って…しかも音だけじゃなくて強弱もつけて、表現だの何だの…やることいっぱい!よくやってるなとつくづく感心します。
だから子供が見落としがないように忘れないように具体的にしっかりとサポートしていかなければと、改めて考えさせられた本でした。
本文中に、
「一番辛いのはお母さまです。発達障害を育てているお母さまは、「しつけがなっていない!」と思われることがたびたびあります。しかし実際に接してみると、どこのご家庭よりもしつけに気をつけているのが発達障害のお子さんを持つお母さま方なのです。」
とありました。この言葉でどれだけのお母さまが救われることか。
ちょうど子供のクラスに発達障害の子がいて、そのお母さんが学校の行事などでまわりに気を遣いながら本当に大変な思いをしている姿を何度も見ています。
発達障害と言っても、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動性障害(ADHD)、限局性学習障害(LD)、運動障害など様々な症状があり、またその症状の出方も個人差がかなりあります。
発達障害は誰のせいでもありません。ましてやお母さんのしつけのせいでもありません。治るものでもないし、障害でもないし、その子の個性です。
本当に素晴らしい内容でとても勉強になる本でした。私も中嶋先生のように寛容になりたい。
-
前の記事

川口マーン恵美 著『証言・フルトヴェングラーかカラヤンか』と、MLMナショナル管オンデマンド・コンサートに宮田大さん(チェロ)のゲスト出演が決定! 2020.07.13
-
次の記事

ブックオフにて掘り出し物のチェロCD。日本フィルが夏休みコンサートを開催。 2020.07.20
同一カテゴリの記事一覧
母さんのひとりビブリオ の記事
- 11月は児童虐待防止推進月間。音楽教育と教育虐待について考える。『父の逸脱 ピアノレッスンという拷問』『ルポ教育虐待』
- 収穫の秋。読書の秋『チェリスト、青木十良』『シュタルケル自伝』。
- 逃走中。と映画『アルゲリッチ 私こそ、音楽!』と書籍マルタ・アルゲリッチ『子供と魔法』
- ---本記事---
- 川口マーン恵美 著『証言・フルトヴェングラーかカラヤンか』と、MLMナショナル管オンデマンド・コンサートに宮田大さん(チェロ)のゲスト出演が決定!
- 科挙を受けるための学校。そしていよいよ科挙の本試験。なんと日本人で科挙に合格した人が過去に1人だけいた!
- キングダムからの、宦官からの、科挙。科挙の学校入学のための願書と採点者。
- 藤原真理さん著の『チェロ、こころの旋律』を読みました。
- 漫画『キングダム』を読んだその足で図書館に。そして宦官へ…。
- 僕のジョバンニ。
- 原田マハさんの『生きるぼくら』を読みました。